
【保存版】AI時代でも変わらない!高評価を受ける指定管理事業提案書6つの法則 – 第1回「行政の意図を理解せよ!」
AIで事業提案書作成が秒速化する時代、それでも評価されるには“行政の意図理解”が必須。指定管理の審査員の本音と現実、AI活用で効率化しつつ差がつく提案内容を徹底解説。現場ヒアリングの重要性、AI指示の極意も紹介。AI×現場力で無敵の提案書を作るための第1法則を学べる保存版記事です。
公開日2025/07/08
更新日2025/07/18
目次
こんにちは。ヤマザキです。
🚀 はじめに – AIで計画書作成が“秒速”になった今こそ
ChatGPTやClaude、Geminiなど、生成AIを活用すれば、事業提案書の素案作成や過去計画書の要点抽出は1日どころか数時間で完成する時代になりました。
私自身も日々AIに執筆を手伝ってもらい、業務効率は爆発的に上がりました。 しかし、ここで多くの指定管理者が陥る落とし穴があります。
💡 AIに書かせるには“あなた自身の解像度”が必要
AIは超優秀な新人部下です。 指示が具体的であればあるほど、期待以上の成果を出してくれます。
でも、逆にこちらの理解が浅いと…
- 「ありきたりで薄い提案書」
- 「行政意図を読み違えたズレた提案書」
が出来上がり、むしろ評価を落とす結果になりかねません。
⚠️ だからこそ、今一度“基本”を学ぶ
今回からお届けするシリーズでは、
「AIに指示を出すためにも必要な、指定管理提案書作成の本質」
を6つの法則に分けて解説していきます。
AIが進化しても変わらない“人間ならではの洞察力”を磨き、 AI活用×現場知見で無敵の提案書を作り上げてください。
🏆 第1の法則:行政サイドの意図を理解せよ!
🎯 この記事が刺さるのは、こんな方!
- 提案書をAIで書けるようになったが、中身が浅く落選続き…
- 審査員の評価ポイントがイマイチ掴めない
- 「AI+現場知見」で最強になりたい指定管理営業マン
🤔 審査員は誰か?
指定管理の審査員はこんな人たちです。
- 市長、副市長、部長クラスの行政幹部
- 大学教授や文化財団理事
- 商工会や自治会長など地域代表
つまり、本業が多忙で一字一句読む時間はない人ばかり。
💡 審査のリアル
- コンサルや担当課職員が作成した「採点表サマリー」だけで評価する審査員もいる
- 資料をパラパラめくり「ふーん、まぁいいんじゃない」で決めることも
この現実を知っているかどうかで、提案書の作り方は変わります。
🔑 高評価のカギ=行政サイドの意図理解
指定管理提案書はあくまで行政が発注主。 こちらが「やりたいからやる」ではなく、行政が求めていることをやる姿勢が大前提です。
💡 提案の極意
1. 行政の要求と自社のやりたいことを一致させる
AIで公募要項や仕様書を要約させると、全体像把握は一瞬です。
しかし、その上で最も重要なのが、 行政がまだうまく言語化できていない課題をこちらから定義すること。
「確かにそれが問題だった」と行政が腑に落ちれば、提案書は単なる応募書類ではなく、解決策そのものとして高評価されます。
2. 課題とゲイン(得たい未来)にアンテナを張る
行政の最終目的は「市民に喜ばれること」「課題解決」です。
例えば…
- 地震直後 → 防災拠点機能強化・耐震補強
- 高齢化進行 → 介護予防・健康寿命延伸
- 子育て世代増加 → 親子イベント・乳幼児室改善
こうした「行政が得たい未来」を想像し、AIに
この公募要項から行政の課題とゲインを抜き出して
と指示を出せば、ポイントを瞬時にまとめてくれます。
3. 立地・地域特性・施設機能を正確に把握する
例えば、
- 市の中心部か郊外か
- 公園一体型か単独施設か
- 築年数、耐震性、規模、バリアフリー状況
これらは現地視察なしでも、AIにGoogle Mapや自治体HPを読ませれば一通り情報収集可能です。
しかし、現場に足を運び、 **「雨の日の駐車場混雑」や「館内で迷う高齢者」**などのリアルを知ることが最終差別化につながります。
4. 世の中の流れを捉える
「SDGs」「DX」「地域共創」「災害レジリエンス」「生成AI」など、 行政が意識しているトレンドワードを提案書に散りばめましょう。
AIに最新トレンドを要約させ、
このトレンドを指定管理計画書のどこに活かせるか提案して
と聞けば、社会性×実行性を兼ね備えた施策アイデアが生成されます。
👂 AIだけではできない「現場ヒアリング」
AIで仕様書分析やデータ整理を終えたら、次に必要なのは現場ヒアリングです。
🎯 その理由は…
- 住民・利用者の声=行政が最も重視する指標
- 現場情報はあなただけのオリジナル資産
💡 ヒアリングポイント
-
カスタマージャーニーを描く 利用者が施設に来る動機、滞在中の感情、帰るときの満足度。
-
住民インタビューや利用者ロープレを行う 「もし自分が子連れの母親だったら…」「高齢の父を連れてきたら…」と憑依する。
-
職員の雑談からヒントを得る 清掃員や受付スタッフの一言に、真の課題が隠れていることが多い。
🤖 AI×現場情報=最強
AIに仕様書読解やトレンド調査を任せ、 自分は現場で一次情報を取りに行く。
この分業ができる営業マンこそ、 これからのAI時代の指定管理者で勝ち続ける人材です。
以下、おしゃれに読みやすい関連記事挿入用マークダウン記法です。
🔗 関連記事
📢 合わせて読みたい!
【至急行動】現場に行け!――事業計画書より“人間関係”で勝つAI時代の指定管理獲得戦略
現場での関係構築とAI活用を掛け合わせる指定管理戦略を詳しく解説しています。 提案書作成だけでなく、“足で稼ぐ情報”の価値も見直してみましょう。
✨ ビジョンパートで“行政理解力”を示せ!
提案書の最後には必ずビジョンを語るパートがあります。
ここで重要なのは、
- 行政や施設理解の深さ
- 指定管理期間を通じてやりきる覚悟
これを伝えることで、 「この会社なら安心して任せられる」と思わせることができます。
💡 AI活用である程度までは書ける
AIに
この施設の目的、課題、行政のゲイン、住民ニーズを踏まえたビジョンパートを書いて
と指示すれば、ある程度のプロトタイプは一瞬で生成されます。
しかし、これだとだれでも作れるありきたりな文章になります。
なので、最後はあなた自身が
- 現場感
- 感情
- 未来への責任
を乗せて仕上げることで、唯一無二の提案書になります。
✅ まとめ
高評価を得る法則①:行政サイドの意図理解
- 行政は発注主。自己満足提案は減点。
- 公募資料はAIで徹底要約、理解を深める。
- 行政が定義できていない課題をこちらから提案する。
- 立地・地域特性・施設機能を正確に把握する。
- 社会トレンドを提案に織り込む。
- AI×現場ヒアリングで唯一無二の内容に。
- ビジョンパートで「この指定管理者なら任せられる」と思わせる。
次回は、第2の法則「要求水準を圧倒的に突破せよ!」についてお届けします。 AI指定管理者では、これからもAI活用×現場力で勝つための記事をどんどん発信していきます!
📝 本日は以上となります!また次回!
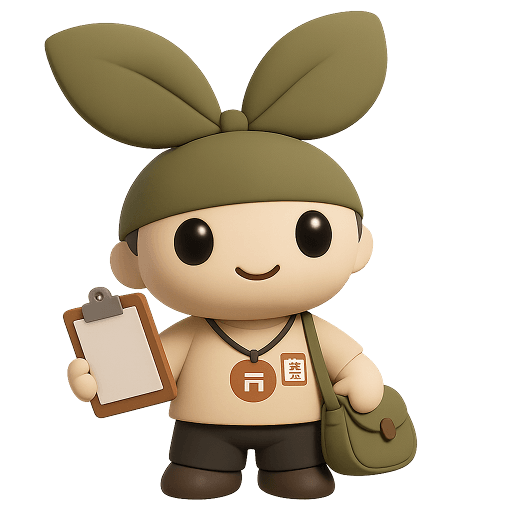
指定管理者制度に携わる皆様の業務効率化と採択率向上をサポートする記事をお届けしています。
ヤマザキは2004年から大学で指定管理者制度を研究し、
2010年からの10年間は、指定管理/PFI/PPPのコンペや運営現場の最前線に立ち続けてきました。
その後はスタートアップとの協業や出資、ハッカソンも数多く主催。「現場」と「未来」双方の知見を活かした情報発信を行っています。
その経験をもとにした本サービス「指定管理者制度AI」では、実際にAIを活用した提案書・企画書作成サービスを展開。 豊富な採択事例データベースと高度な自然言語処理技術により、要点整理から文書構成の最適化まで包括的にサポートします。
自治体要件の読み取り、競合分析、予算計画の策定など、指定管理者応募に必要な業務を効率化し、 質の高い提案資料を短時間で作成できる専門AIツールを提供しています。