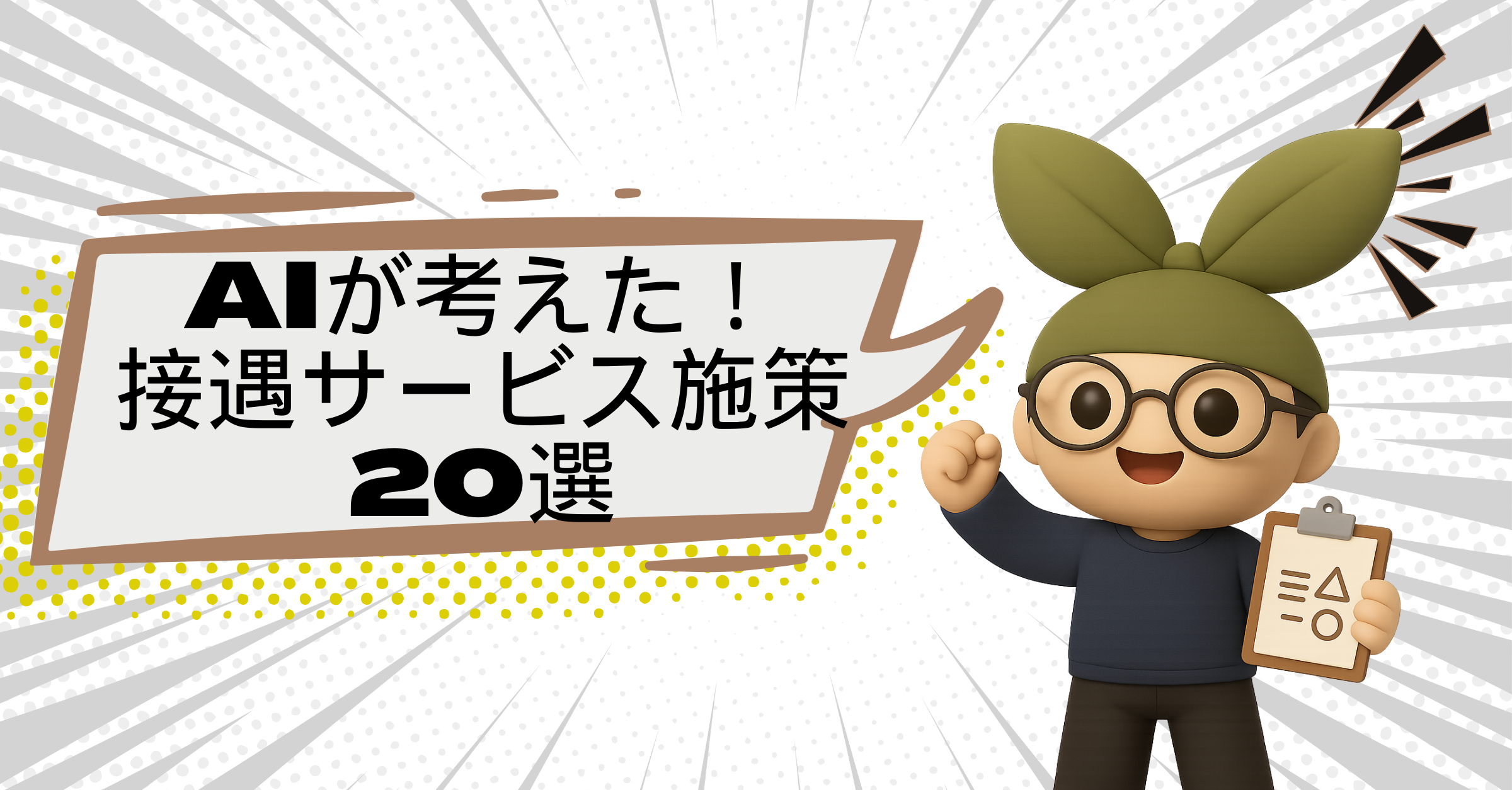
【コピペ歓迎】AIと考えるシリーズ:事業計画書で差がつく接遇提案20選<2025年最新版>
指定管理者営業担当必見!事業計画書の接遇提案で他社を圧倒する具体的施策20選。コピペOKの提案文例、数値目標、予算計画、年間スケジュール全て掲載。「丁寧な対応します」レベルでは勝てない現代の選定基準に対応した戦略的提案書作成術。利用者満足度90%、苦情解決72時間以内等、審査員が評価する実績ベース内容で受注率大幅UP。AIと考えるシリーズ2025年最新版。
公開日2025/09/03
更新日2025/10/30
目次
みなさん、こんにちは。指定管理者制度AI編集長のヤマザキです。
「また今月も事業計画書の締切が...」 「接遇向上って書いたけど、具体的に何すればいいの?」 「他社に差をつけられる提案内容が思い浮かばない...」
指定管理者の営業担当として事業計画書を作成されている皆さん、毎回の提案書作成、お疲れさまです。 特に接遇・サービス向上の部分って、
「丁寧な対応をします」 「研修を実施します」
みたいな当たり前のことしか書けなくて、困りますよね。
でも安心してください。 今日は、そのまま事業計画書にコピペできる、具体的で差別化できる接遇施策を20個ご紹介します。 実際に他の指定管理者が実施して成果を上げている内容ばかりなので、提案の説得力もバッチリです。
この記事でわかること
- 事業計画書にそのまま使える接遇施策の具体的な書き方20選
- 他社と圧倒的に差がつく数値目標とスケジュールの設定方法
- 審査員が「お!」と注目する独自性のある取り組み事例
- 予算計画まで含めた実現可能性の高い提案テンプレート
- 次期更新時のアピールポイントになる継続的改善システム
なぜ接遇提案で勝負が決まるのか
ハッキリ言います。今の指定管理者選定では、接遇・サービス向上提案の質で9割決まるんです。
理由は簡単。 施設管理や運営ノウハウはもう差がつかないレベルまで来ているからです。 どこも似たような提案になる中で、「利用者目線のサービス向上」だけが最後の差別化ポイントなんですね。
実際に最近の選定結果を見ると、価格点で負けていても、接遇・サービス提案で逆転勝利するケースが激増しています。 審査員も「結局、利用者が喜んでくれるかどうか」を一番重視しているんです。
つまり、この部分の提案さえしっかりしていれば、受注確率は格段に上がります。 今日紹介する内容を参考に、ライバルをごぼう抜きしちゃいましょう!
事業計画書にコピペOK!差がつく接遇提案20選
【基盤整備・体制構築編】※そのまま使えます
1. 接遇マニュアルの策定と年2回改定システム
【事業計画書記載例】
■接遇統一化システムの構築
・利用者対応の統一基準を明文化した接遇マニュアルを策定します。
・蓄積された苦情データや利用者アンケート結果を反映し、年2回(4月・10月)の定期改定を実施します。
・全職員が携帯可能なポケットサイズ版も作成し、現場での即座な確認を可能にします。
・新人研修での必須教材として活用し、対応品質の標準化を図ります。
【数値目標】
・接遇マニュアル理解度テスト:全職員90点以上
・マニュアル改定による改善実施率:年間20項目以上2. 苦情対応責任者制度の導入
【事業計画書記載例】
■専任苦情対応責任者(総括責任者)の配置
・苦情対応専門の総括責任者を1名専任配置します。
・日常からの準備体制監督、苦情記録データの整理報告、苦情回避会議の設営運営を担当します。
・トラブル発生から解決までの一元管理により、対応の迅速化と品質向上を実現します。
【実施体制】
・苦情対応委員会の設置(月1回定例開催)
・苦情対応責任者、受付担当責任者、その他必要スタッフで構成
・対応方法協議、改善策検討、再発防止策の立案・実行を担当3. 「情報・苦情処理簿」データベース化
【事業計画書記載例】
■苦情対応データベースシステムの構築
・トラブル内容、対応方法、日時、場所、通知方法を記録するデジタルデータベースを構築します。
・過去事例の検索・分析・共有を可能にし、同一トラブルの再発を完全防止します。
・蓄積されたデータを基に、予防的改善策を継続的に立案・実施します。
【導入効果】
・過去事例検索時間:従来比80%短縮
・同種トラブル再発率:前年度比50%削減目標【人材育成・研修編】※数値目標がポイント
4. 新任職員向け集中接遇研修プログラム
【事業計画書記載例】
■新任職員2週間集中接遇研修の実施
・入職から2週間以内に8時間の接遇研修を必須受講とします。
・基本的なマナー、多様性対応、緊急時対応を体系的に習得させます。
・ロールプレイング中心の実践的内容で、即戦力化を実現します。
・研修修了認定試験(85点以上)の合格を配置条件とします。
【年間実施計画】
・新任研修:年6回実施予定
・受講対象者:全新規配置職員(年間予想15名)
・研修講師:外部専門講師2名 + 内部講師3名5. ユニバーサルマナー検定2級取得推進制度
【事業計画書記載例】
■全職員ユニバーサルマナー検定2級取得計画
・全職員にユニバーサルマナー検定2級の取得を義務化します。
・3年以内の100%取得を目標とした段階的実施計画を策定します。
・受検費用は当社が全額負担、合格者には資格手当月額3,000円を支給します。
・多様性に配慮した高品質サービスの提供を実現します。
【取得スケジュール】
・1年目:管理職・リーダー職(10名)
・2年目:一般職員(15名)
・3年目:新規配置職員・未合格者(5名)
・取得率目標:3年後100%達成6. 月例ロールプレイング研修制度
【事業計画書記載例】
■実践的ロールプレイング研修の定期実施
・「トラブル対応マニュアル」に基づく月例研修を実施します。
・困難事例を中心とした実践的内容で対応力を継続向上させます。
・外部講師による専門研修を年2回実施し、最新の接遇技術を導入します。
・全職員参加型で経験とノウハウを組織全体で共有します。
【実施概要】
・開催頻度:毎月第2土曜日(年12回)
・参加対象:全職員必須参加
・研修時間:1回2時間
・外部講師研修:年2回(6月・12月)【バリアフリー・多様性対応編】※具体的数量がカギ
7. 車椅子無料貸出サービス運営
【事業計画書記載例】
■車椅子無料貸出サービスの充実
・施設内に車椅子10台を常備し、利用者への無料貸出を実施します。
・使用後の清拭・点検を徹底し、安全で清潔な車椅子を提供します。
・利用記録簿による適切な管理体制を構築します。
・定期メンテナンス(月1回)により、常時稼働可能な状態を維持します。
【サービス仕様】
・配置台数:10台(予備2台含む)
・設置場所:受付カウンター横専用ラック
・対応時間:施設開館時間内随時
・メンテナンス:専門業者による月次点検8. コミュニケーション支援ツールの配備
【事業計画書記載例】
■聴覚障害者向けコミュニケーション支援の強化
・筆談器5台を受付に常備し、聴覚に不安のある利用者をサポートします。
・音声拡聴器3台を配置し、難聴の方への配慮を充実させます。
・全職員に筆談器・拡聴器の使用方法を習得させ、自然な対応を実現します。
・支援ツール利用可能を示すピクトグラムを受付に表示します。
【配備計画】
・筆談器:5台(各受付ポイントに配置)
・音声拡聴器:3台(メイン受付・サブ受付・事務室)
・職員研修:使用方法マスター研修を年1回実施9. 多言語対応システム導入
【事業計画書記載例】
■AI音声翻訳機による多言語対応サービス
・音声翻訳機「ポケトーク」を全受付ポイント(3箇所)に配置します。
・74言語対応により、多国籍利用者へのスムーズな案内を実現します。
・基本的な外国語挨拶(英語・中国語・韓国語)を全職員が習得します。
・多言語案内表示を主要エリアに設置し、利用環境を向上させます。
【導入仕様】
・配置台数:3台(メイン受付・サブ受付・総合案内)
・対応言語:74言語(音声・テキスト翻訳)
・職員研修:操作方法習得研修を年2回実施
・案内表示:4ヶ国語表記(日・英・中・韓)10. 視覚サポートサービス充実
【事業計画書記載例】
■視覚に配慮した情報提供サービス
・大活字版施設案内(16ポイント)を50部作成し、受付で配布します。
・点字版施設案内を50部準備し、視覚障害者のニーズに対応します。
・色覚に配慮した案内表示デザインに全面改修します。
・音声案内システムの導入を検討し、情報アクセシビリティを向上させます。
【整備内容】
・大活字版案内:50部(年2回更新)
・点字版案内:50部(専門業者作成)
・案内表示改修:カラーユニバーサルデザイン準拠
・音声案内:主要ルート4箇所への設置検討【意見収集・モニタリング編】※PDCAがポイント
11. 利用者満足度調査システム
【事業計画書記載例】
■戦略的利用者満足度調査の実施
・春季(5月)・秋季(11月)の年2回、利用者満足度調査を実施します。
・5段階評価による定量分析と自由記述による定性分析を実施します。
・利用目的別・年代別・利用頻度別の詳細分析により課題を特定します。
・調査結果と改善計画を館内掲示により利用者に公開します。
【調査概要】
・実施回数:年2回(5月・11月)
・回収目標:各回200サンプル以上
・調査項目:接遇・施設・プログラム・総合満足度(各5段階)
・目標値:総合満足度90%以上維持12. 意見箱戦略配置システム
【事業計画書記載例】
■効果的意見収集のための意見箱配置計画
・施設内5箇所への意見箱戦略配置により、利用者の声を効率収集します。
・受付、各トレーニングルーム、会議室エリア、カフェテリア、メイン出入口に設置します。
・週1回の定期回収と48時間以内の初回対応を徹底します。
・匿名意見への丁寧な回答を館内掲示により全利用者と共有します。
【運用体制】
・設置箇所:5箇所(各利用エリアの動線上)
・回収頻度:毎週火曜日定期回収
・対応時間:48時間以内の初回回答
・共有方法:月次で対応状況を館内掲示13. デジタル意見収集システム
【事業計画書記載例】
■24時間対応オンライン意見受付システム
・施設公式ホームページに意見投稿フォームを設置します。
・24時間365日受付可能な体制により、利用者の利便性を向上させます。
・スマートフォン最適化により、若年層の意見収集を強化します。
・48時間以内の初回返信を徹底し、迅速な対応姿勢を示します。
【システム仕様】
・受付時間:24時間365日
・対応端末:PC・スマートフォン・タブレット対応
・返信体制:48時間以内初回返信100%
・年間目標:オンライン意見100件以上収集14. 第三者評価システム導入
【事業計画書記載例】
■ミステリーショッピングリサーチによる客観評価
・専門調査会社による覆面調査を四半期ごと(年4回)実施します。
・接遇対応・施設管理状況・情報提供の3分野で客観評価を取得します。
・調査結果を基にした具体的改善計画の立案・実行を行います。
・評価向上状況を自治体に定期報告し、運営品質の透明性を確保します。
【実施計画】
・調査頻度:四半期ごと年4回
・調査内容:接遇・施設管理・情報提供(各10項目評価)
・目標点数:総合評価85点以上維持
・改善サイクル:調査→分析→改善→効果測定【予防・トラブル対応編】※スピード感が勝負
15. 予防的コミュニケーションシステム
【事業計画書記載例】
■積極的利用者コミュニケーションによるトラブル予防
・職員による2時間おきの施設内巡回を実施します。
・利用者への積極的な声かけにより、潜在的問題の早期発見を実現します。
・「困る前に解決」の予防的アプローチで利用者満足度を向上させます。
・巡回記録による情報共有で組織全体の対応力を強化します。
【実施体制】
・巡回頻度:2時間おき(開館時間内)
・担当者:各時間帯責任者が実施
・記録方法:巡回チェックシートによる記録・共有
・効果測定:予防解決件数の月次集計16. VIP利用者ヒアリングシステム
【事業計画書記載例】
■サイレントクレーマー発掘のための個別ヒアリング
・月間利用回数上位50名を対象とした年1回の個別ヒアリングを実施します。
・「不満があっても言わない」利用者の潜在ニーズを積極発掘します。
・長期利用者の視点から施設改善のヒントを収集します。
・VIP向け特別サービスの検討により利用者ロイヤリティを向上させます。
【実施概要】
・対象者:月間利用上位50名(年間延べ600名相当)
・実施時期:毎年2-3月
・ヒアリング時間:1人30分程度
・実施場所:専用相談室でプライバシーに配慮17. 72時間完結システム
【事業計画書記載例】
■迅速トラブル解決システムの構築
・トラブル発生から72時間以内の完全解決システムを構築します。
・初期対応→原因分析→改善策立案→利用者報告の一連フローを標準化します。
・複数職員での対応体制により、公平性・客観性を確保します。
・解決プロセスの記録・蓄積により、組織的対応力を継続向上させます。
【対応フロー】
・24時間以内:初期対応・事実確認
・48時間以内:原因分析・改善策立案
・72時間以内:改善実施・利用者報告
・1週間後:効果確認・フォローアップ18. 改善の見える化システム
【事業計画書記載例】
■利用者参加型改善システムの構築
・利用者意見・要望とその対応状況を月1回館内掲示により公開します。
・改善前後の写真付き報告により、変化を視覚的に提示します。
・「あなたの声が形になりました」を実感できる双方向コミュニケーションを実現します。
・透明性の高い運営により、利用者との信頼関係を強化します。
【公開内容】
・月次改善実績:改善件数・内容・効果
・写真付きレポート:ビフォーアフター比較
・今後の改善予定:計画中の取り組み紹介
・利用者からの感謝の声:改善への評価紹介【システム・継続改善編】※ここで差がつく
19. 危機管理体制強化
【事業計画書記載例】
■包括的危機管理システムの構築
・反社会的組織対応研修を年1回実施し、全職員の対応力を強化します。
・警察署との連携協定締結により、緊急時の迅速対応体制を確立します。
・緊急事態発生時の通報・連絡・避難システムを整備します。
・利用者・職員双方の安全確保を最優先とした危機管理体制を構築します。
【体制整備】
・研修実施:年1回全職員対象
・警察連携:○○警察署との協定締結
・緊急連絡網:24時間対応可能な連絡体制
・避難誘導:定期訓練年2回実施20. PDCAマネジメントシステム
【事業計画書記載例】
■継続的品質向上システムの確立
・Plan-Do-Check-Actionサイクルによる体系的品質管理を実施します。
・「安全・安心」「迅速・的確」「ホスピタリティ」の3軸で定期評価を行います。
・月次・四半期・年次での多段階効果測定により改善を継続します。
・自治体への定期報告により透明性を確保し、次期指定更新への実績を蓄積します。
【評価指標】
・利用者満足度:90%以上維持
・苦情件数:前年度比20%削減
・苦情解決率:100%(72時間以内)
・職員研修受講率:100%
・各種資格取得率:100%提案書に使える数値目標・予算・スケジュール
年間実施スケジュール(そのまま使用OK)
新たに受託してから、以下のようなスケジュールですすめると記載しましょう。 より具体性が高まり、得点UPにつながります。
【4月】
・接遇マニュアル改定
・新年度職員研修実施
・第1四半期ミステリーショッピング
【5月】
・春季利用者満足度調査
・ユニバーサルマナー検定受検(第1期)
・車椅子等設備点検
【6月】
・外部講師研修実施
・VIPヒアリング準備
・第1四半期実績評価
【7月-9月】
・月例研修継続実施
・夏季繁忙期対応強化
・第2四半期ミステリーショッピング
【10月】
・接遇マニュアル改定(第2回)
・秋季職員研修
・年末年始準備
【11月】
・秋季利用者満足度調査
・ユニバーサルマナー検定受検(第2期)
・第3四半期実績評価
【12月】
・外部講師研修実施(第2回)
・年間実績取りまとめ
・次年度計画策定
【1-3月】
・VIPヒアリング実施
・年度実績評価
・次年度準備・引継ぎ予算計画例(5年間継続可能)
予算まできっちり定義していると、さらに信頼が増します。
【初期導入費用】
・接遇マニュアル作成:15万円
・データベースシステム:30万円
・車椅子10台購入:25万円
・多言語翻訳機3台:15万円
・筆談器・拡聴器:8万円
小計:93万円
【年間運営費用】
・外部研修講師費:24万円(月2万円×12回)
・ミステリーショッピング:20万円(5万円×4回)
・各種検定受験料:15万円(職員30名想定)
・資格手当:108万円(3,000円×30名×12ヶ月)
・満足度調査費:10万円(5万円×2回)
小計:177万円
年間総額:270万円(初年度のみ363万円)他社に差をつける提案のコツ
審査員が「お!」と思うポイント
1. 具体的な数値目標 「研修を実施します」ではなく「月例2時間研修×12回、受講率100%達成」
2. 継続可能性の担保 「予算○○万円で5年間継続実施」「職員資格手当制度で定着促進」
3. 効果測定システム 「利用者満足度90%以上」「苦情解決72時間以内100%」
4. 地域特性への配慮 「高齢化率○%の地域特性に配慮したバリアフリー強化」
よくある失敗提案を避ける方法
❌ NG例:「丁寧な接遇を心がけます」
⭕ OK例:「接遇マニュアル策定→年2回改定→理解度テスト90点以上」
❌ NG例:「研修を実施します」
⭕ OK例:「月例ロールプレイング研修2時間×12回、外部講師年2回招聘」
❌ NG例:「利用者の声を聞きます」
⭕ OK例:「意見箱5箇所設置、オンライン24時間受付、48時間以内返信」まとめ:勝てる提案書の作り方
営業担当の皆さん、いかがでしたか?今日紹介した20の施策は、どれも実際に他の指定管理者が実施して成果を上げているものばかりです。
すぐに使える提案のポイント
- 具体的な数値を必ず入れる
- 実施スケジュールを明確にする
- 予算計画を現実的に設定する
- 継続可能性をアピールする
- 効果測定方法を明示する
最終チェックリスト
□ 他社との差別化ポイントが明確か?
□ 実現可能な予算・人員計画になっているか?
□ 数値目標が具体的に設定されているか?
□ 継続的改善システムが組み込まれているか?
□ 地域特性への配慮が盛り込まれているか?提案書作成、頑張ってください!この内容を使って、ライバルに圧勝しちゃいましょう!
皆さんの受注成功を、心から応援しています。何か困ったことがあれば、いつでもお気軽にご相談ください!
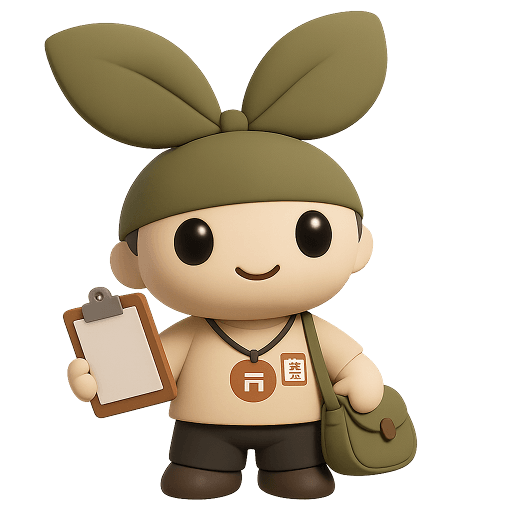
指定管理者制度に携わる皆様の業務効率化と採択率向上をサポートする記事をお届けしています。
ヤマザキは2004年から大学で指定管理者制度を研究し、
2010年からの10年間は、指定管理/PFI/PPPのコンペや運営現場の最前線に立ち続けてきました。
その後はスタートアップとの協業や出資、ハッカソンも数多く主催。「現場」と「未来」双方の知見を活かした情報発信を行っています。
その経験をもとにした本サービス「指定管理者制度AI」では、実際にAIを活用した提案書・企画書作成サービスを展開。 豊富な採択事例データベースと高度な自然言語処理技術により、要点整理から文書構成の最適化まで包括的にサポートします。
自治体要件の読み取り、競合分析、予算計画の策定など、指定管理者応募に必要な業務を効率化し、 質の高い提案資料を短時間で作成できる専門AIツールを提供しています。