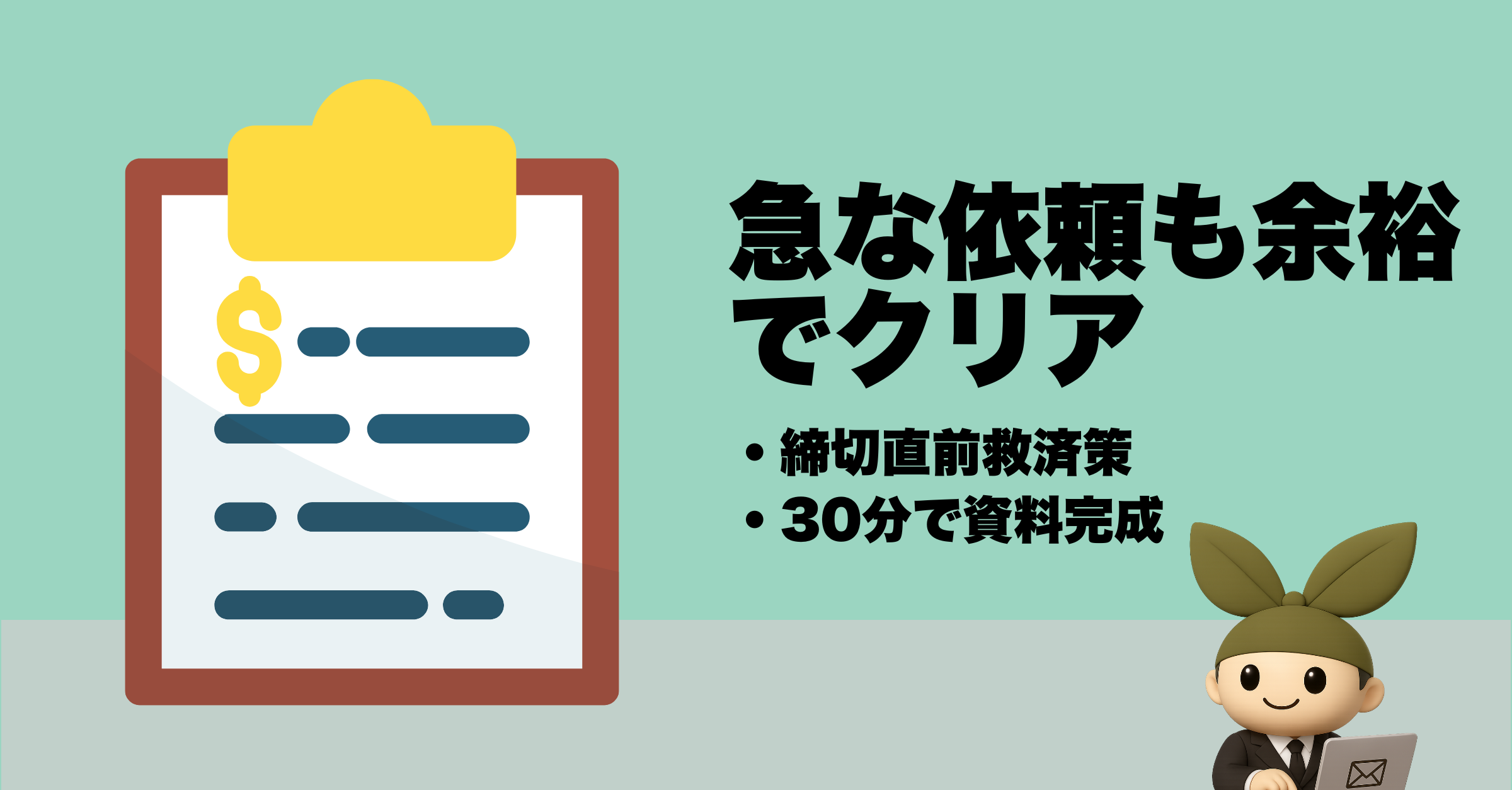
【朗報】「30分で神資料」作成術|ChatGPT活用で残業地獄から脱出する方法
指定管理者必見!「明日までに資料作って」の急な依頼でも30分で完成させるChatGPT活用術を完全解説。年度事業報告書、緊急事態対応、利用料金改定提案など現場で使える5つのテンプレート付き。たたき台から完成資料への仕上げ方、自治体評価のポイント、導入時の注意点まで実践的に紹介。資料作成地獄から脱出して本来業務に集中しよう。
公開日2025/08/10
更新日2025/08/11
目次
みなさん、こんにちは。 指定管理者制度AI編集長のヤマザキです。
・担当課「すいません。明日までに来期の年度事業計画の基礎資料提出してくれませんか?」 ・指定管理事業者担当「え、明日ですか。。。」 ・担当課「えええ。ちょっと、課長が急に必要になったみたいで。。。」 ・指定管理事業者担当「ああ、なるほど。(これ、伝えるの忘れてたな。。。)わかりました!やります!(今夜は徹夜かな~)」
こんな経験、みなさんにもありませんか? 自治体から、 「来週までに利用状況の分析資料を」 「明後日の会議で改善提案書を」 と突然依頼が来て、頭を抱えたこと。
私はしょっちゅうありました。。。 そういった限られた時間で質の高い資料を作るのは、本当に大変ですよね。
でも、心配ありません。 今日お話しする「ChatGPTを使った資料のたたき台自動作成術」を覚えれば、そんな無茶ぶりから来る焦りから解放されるんです。 実際に、私も翌朝の朝活30分で見事な資料のベースを完成させ、「おお仕事早いですね!」と、担当課の方に喜んでいただくことができました。
この記事でわかること
□ 締切直前・無茶ぶりでも慌てない、AI活用の資料作成術 □ 指定管理者の現場で実際に使える5つのテンプレート □ 「たたき台」から「完成資料」への効率的な仕上げ方 □ 自治体や審査委員会で評価される資料の作り方 □ 導入時の注意点と失敗を避けるコツ
なぜ今、資料作成の効率化が必要なのでしょうか
指定管理者として日々施設運営に携わっているみなさんなら、資料作成がいかに時間を取られる作業かご存知でしょう。
利用者対応、設備管理、イベント企画、スタッフマネジメント...やるべきことは山積みなのに、「資料作成で一日が終わってしまった」なんてこと、よくありますよね。
しかも、求められる資料の質は年々高くなっています。
単なる数字の羅列ではなく、分析結果、改善提案、将来展望まで盛り込んだ戦略的な内容が期待されているんです。
そんな中で「明日までに」「来週の会議で」という急な依頼が舞い込むと、もう手が回らない。
夜遅くまで残業して、家族との時間も削って...そんな状況を何度も経験されているのではないでしょうか。
でも、ChatGPTのような生成AIを味方につけると、この状況は劇的に変わります。
「たたき台」を一瞬で作ってもらい、それをベースに肉付けしていく。
この方法なら、時間も大幅に短縮でき、質の高い資料も作れるんです。
基本的な仕組み:30分で資料のたたき台完成
AIを使った資料作成の基本的な流れは、とてもシンプルです。
まず、作りたい資料の
「目的」 「対象者」 「盛り込みたい内容」
を整理します。
そして、それをChatGPTに伝えて、資料の構成案とたたき台を作ってもらうんです。
例えば、こんな感じで依頼します:
以下の条件で、運営委員会向けの利用状況分析資料のたたき台を作成してください。
【資料の目的】
・今年度上半期の利用状況を分析し、課題と改善策を提示する
・下半期の運営方針を決めるための判断材料とする
【対象者】
・市の担当課長、運営委員会委員(地域代表3名、有識者2名)
【盛り込みたい内容】
・利用者数の推移(前年同期比較)
・稼働率の分析
・利用者アンケート結果
・収支状況
・下半期に向けた改善提案
【資料の分量】
・A4で10ページ程度のPowerPoint想定すると、ChatGPTが以下のような構成案とたたき台を作ってくれます:
【タイトル】○○文化センター 令和6年度上半期運営状況報告書
1. エグゼクティブサマリー
- 今期の主要成果と課題を3つのポイントで整理
- 下半期の重点施策を明確化
2. 利用状況の推移分析
- 月別利用者数グラフ(前年対比)
- 施設別稼働率の比較表
- 主要イベントの集客実績
3. 利用者満足度調査結果
- アンケート回答者属性
- 満足度スコアの推移
- 自由記述から見える改善要望
このように、全体の骨組みから各章の内容まで、一気に整理してもらえるんです。
指定管理者の現場で使える5つのテンプレート
ここからは、実際の現場でよく求められる資料パターン別に、具体的なプロンプト例をご紹介しますね。
テンプレート1:年度事業報告書
【年度事業報告書作成プロンプト】
以下の情報をもとに、自治体提出用の年度事業報告書のたたき台を作成してください。
# 基本情報
・施設名:{{施設名}}
・報告期間:{{年度}}
・管理者:{{団体名}}
# 必須項目
□ 運営方針と重点目標の達成状況
□ 利用実績(利用者数・稼働率・収支)
□ 実施事業の成果と評価
□ 利用者サービス向上の取り組み
□ 施設の維持管理状況
□ 次年度に向けた課題と改善計画
# 作成条件
・A4で15-20ページ想定
・自治体の担当者が読みやすい構成
・数値は表とグラフで見やすく表現
・写真やイラストの挿入箇所も提案
# 参照情報
□ ここにAIに参照してほしい定性情報や実績データ、特記事項を箇条書きで入力 or 参照データを添付した場合は「添付資料を参照してください」と記述テンプレート2:緊急事態対応報告書
【緊急事態対応報告書作成プロンプト】
以下の緊急事態について、自治体への報告書のたたき台を作成してください。
# 報告書の目的
・発生した事案の正確な記録
・対応プロセスの検証
・再発防止策の提示
# 必須構成
□ 事案の概要(5W1H)
□ 発生時の状況と初期対応
□ 関係機関との連携状況
□ 利用者・近隣への影響と対応
□ 原因分析と課題の整理
□ 再発防止策と改善計画
□ 今後の危機管理体制強化案
# 留意点
・時系列で客観的に記述
・責任の所在を明確化
・改善策は具体的かつ実現可能に
# 参照情報
□ ここにAIに参照してほしい定性情報や実績データ、特記事項を箇条書きで入力 or 参照データを添付した場合は「添付資料を参照してください」と記述テンプレート3:利用料金改定提案書
【利用料金改定提案書作成プロンプト】
以下の条件で、利用料金改定に関する提案書のたたき台を作成してください。
# 提案の背景
・現行料金体系の課題
・周辺施設との比較分析
・運営コストの変動要因
# 検討資料
□ 近隣類似施設の料金比較表
□ 利用者アンケートでの料金に関する意見
□ 改定による収支予測
□ 激変緩和措置の検討
□ 実施スケジュール案
# 配慮事項
・利用者への影響を最小限に
・社会情勢を踏まえた妥当性
・段階的実施の可能性
# 参照情報
□ ここにAIに参照してほしい定性情報や実績データ、特記事項を箇条書きで入力 or 参照データを添付した場合は「添付資料を参照してください」と記述テンプレート4:指定管理者選定プレゼン資料
【指定管理者選定プレゼン資料作成プロンプト】
以下の条件で、指定管理者選定のプレゼンテーション資料のたたき台を作成してください。
# プレゼンの目的
・当団体の管理運営能力をアピール
・具体的で実現可能な提案内容の提示
・地域への貢献意欲を示す
# 必須スライド構成
□ 団体概要と実績紹介
□ 施設運営の基本方針
□ 利用者サービス向上策
□ 地域連携・協働の取り組み
□ 管理運営体制と人材配置
□ 収支計画と財務安定性
□ 質疑応答想定問答集
# プレゼン条件
・持ち時間:{{分}}
・審査員:{{審査員構成}}
・評価ポイント:{{重視項目}}
※ここに団体の強み、独自提案、過去実績を入力テンプレート5:利用者満足度調査分析レポート
【利用者満足度調査分析レポート作成プロンプト】
以下のアンケート結果をもとに、利用者満足度調査の分析レポートのたたき台を作成してください。
# 分析の視点
・満足度の全体傾向と前回比較
・項目別の詳細分析
・利用者属性別の特徴
・自由記述からの課題抽出
# レポート構成
□ 調査概要(方法・期間・回答数)
□ 満足度総合評価
□ 項目別満足度分析
□ 利用者属性別クロス分析
□ 自由記述の定性分析
□ 改善要望への対応方針
□ 次回調査に向けた改善点
# 出力形式
・グラフや表を多用した視覚的な構成
・改善アクションプランも併記
# 参照情報
□ ここにAIに参照してほしい定性情報や実績データ、特記事項を箇条書きで入力 or 参照データを添付した場合は「添付資料を参照してください」と記述実践のコツ:「たたき台」を「完成品」にする仕上げ術
AIが作ってくれた「たたき台」は、あくまでスタート地点です。 ここから、みなさんの現場経験と専門知識を加えて、説得力のある資料に仕上げていきましょう。 とはいえ、それらを加えるときも、AIにお願いしながら追記していきましょう。
チェックポイント1:数字の根拠を明確にする □ データの出典を明記する □ 比較対象の条件を統一する □ 計算過程がわかるよう注釈を入れる
チェックポイント2:現場の実情を反映させる □ 地域特性や利用者の声を盛り込む □ 季節変動や外部要因の影響を考慮する □ 実現可能性を現実的に評価する
チェックポイント3:読み手を意識した表現に調整 □ 専門用語には説明を併記する □ 結論を先に、根拠を後に配置する □ ビジュアル要素で理解しやすくする
注意!!:細かく・具体的にAIへ依頼しよう。
AIが作ってくれた資料はおそらく論理がしっかり通ったわかりやすい資料です。 とはいえ、まだまだ専門性だったり、あなたの会社固有の知識が足りません。 そこを補うには、あなたが持っている知識を、細かく具体的にAIへ指示を出していく必要があります。
(例)あなた(AI)が出力した○○をわかりやすく解説して、注釈として最終ページに記載してください。
成功のポイント:地域密着型の資料作りを心がける
指定管理者の資料で最も大切なのは、「この地域の、この施設ならではの内容」になっているかどうかです。
AIは優秀ですが、みなさんの現場で培った経験や地域への愛情までは理解できません。
ポイント1:地域の特色を必ず盛り込む 人口構成、産業構造、文化的背景など、その地域だからこその文脈を資料に織り込みましょう。 例えば、「高齢化率が県平均を上回る当地域では、健康増進プログラムへのニーズが特に高く...」といった具合です。
ポイント2:利用者の「生の声」を活用する アンケートの数値だけでなく、日頃の会話で聞いた利用者の感想や要望を盛り込むと、資料に温度感が生まれます。 もちろん、個人が特定されないよう配慮は必要ですが。
ポイント3:「できること」と「できないこと」を正直に 完璧な提案よりも、現実的で持続可能な内容の方が信頼されます。 制約があるなら、その中でベストを尽くす姿勢を示しましょう。
注意点とリスク対応
AI活用の資料作成で気をつけたいポイントもいくつかあります。
個人情報の取り扱いに注意 利用者の個人情報や施設の機密情報をAIに入力するのは避けてください。 データを匿名化したり、「利用者A」「施設B」のような表現に置き換えてから使いましょう。
事実確認は必ず人間が行う AIが生成した内容に事実誤認がないか、必ずチェックしてください。 特に数値や法的な内容については、元資料と照合することが大切です。
著作権への配慮 AIが提案する表現や構成が、他の資料からの引用になっていないか注意しましょう。 心配な場合は、表現を自分なりにアレンジすることをお勧めします。
一緒に、余裕のある資料作成を実現しましょう
みなさん、いかがでしたでしょうか。 「締切に追われる資料作成」から「余裕を持った質の高い資料作り」への転換、なんだか実現できそうな気がしてきませんか?
AIを活用した資料作成は、決して「手抜き」ではありません。 むしろ、効率化で生まれた時間を、より創造的で付加価値の高い業務に振り向けることができる、とても前向きな取り組みなんです。
利用者の方々との対話により多くの時間を使えるようになったり、新しい企画を考える余裕が生まれたり、職員の皆さんとのコミュニケーションを深められたり。 そんな良い循環が生まれることを、私は確信しています。
最初は慣れないかもしれませんが、「できる範囲で」始めてみてください。 今日ご紹介したテンプレートの中から、まずは一つ選んで試してみる。 それだけで十分です。
みなさんの施設が、地域の方々にとってより魅力的で、愛される場所になることを心から願っています。 そして、その実現のお手伝いができるなら、これほど嬉しいことはありません。
一緒に、もっと余裕のある、そして充実した施設運営を目指していきましょう。
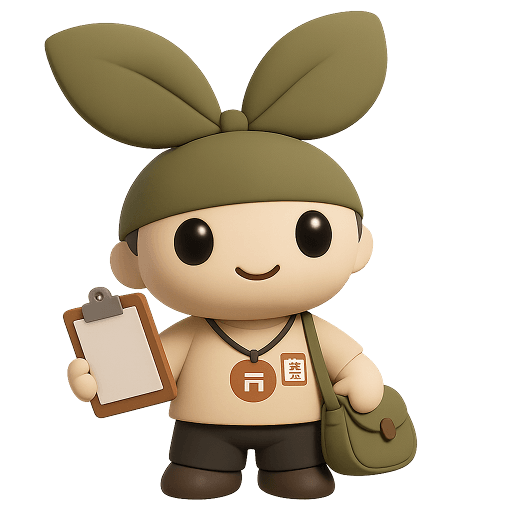
指定管理者制度に携わる皆様の業務効率化と採択率向上をサポートする記事をお届けしています。
ヤマザキは2004年から大学で指定管理者制度を研究し、
2010年からの10年間は、指定管理/PFI/PPPのコンペや運営現場の最前線に立ち続けてきました。
その後はスタートアップとの協業や出資、ハッカソンも数多く主催。「現場」と「未来」双方の知見を活かした情報発信を行っています。
その経験をもとにした本サービス「指定管理者制度AI」では、実際にAIを活用した提案書・企画書作成サービスを展開。 豊富な採択事例データベースと高度な自然言語処理技術により、要点整理から文書構成の最適化まで包括的にサポートします。
自治体要件の読み取り、競合分析、予算計画の策定など、指定管理者応募に必要な業務を効率化し、 質の高い提案資料を短時間で作成できる専門AIツールを提供しています。