
AI画像生成の落とし穴:指定管理者が陥りがちな誤解と実践的対策
みなさん、こんにちは。指定管理者制度AI編集長のヤマザキです。AI画像生成は便利ですが、提案書で使う際は注意が必要です。物理的におかしな構造、日本の法令無視、利用者の偏りなど、審査で減点される落とし穴があります。具体的な指示方法、チェックポイント、著作権対策まで、40-50代の方にもわかりやすく解説します。
公開日2025/08/04
更新日2025/08/08
目次
みなさん、こんにちは。 指定管理者制度AI編集長のヤマザキです。
「AIで作った画像だから大丈夫だろう」
最近、提案書にAI画像を使う事業者の方が増えていますね。確かに便利なツールですが、実はちょっとした落とし穴があるんです。
先日、ある方から「AI画像を使ったら審査でマイナス評価を受けた」という相談をいただきました。詳しく聞いてみると、画像の中身に問題があったようなんです。
今日は、AI画像生成でよくある問題と、それを避けるためのコツをお話しします。難しい話ではありませんので、最後までお付き合いください。
この記事でわかること
- AI画像生成で発生しがちな問題パターンと対策
- 指定管理者業務でAI画像を安全に活用する手法
- 画像の品質チェックポイント
- 自治体審査で評価される画像作成のコツ
- AI生成画像の著作権リスクへの対処法
AI画像で気をつけたいポイント
まず、AI画像でよく起こる問題をいくつかご紹介しますね。「えっ、そんなことがあるの?」と思われるかもしれませんが、意外とよくあることなんです。
おかしな絵になってしまうパターン
AIって、時々「あれっ?」という画像を作ってしまうんです。
こんな問題が起きることがあります:
- 建物の構造がおかしい(階段が途中で変な形になっているなど)
- 人の手足の指の数が違う
- 影の向きがバラバラ
- 物が浮いているように見える
パッと見ると気づかないのですが、審査の方がじっくり見ると「あれ?なんか変だな」と思われて、減点につながることもあるんです。
日本の決まりを知らないAI
AIの多くは海外で作られているので、日本の法律や決まりをよく知らないんです。そのため、日本では「これはダメでしょ」という画像を作ってしまうことがあります。
気をつけたいポイント:
- 車椅子用のスロープが急すぎる
- 通路が狭すぎて避難に問題がありそう
- 消防設備がちゃんと描かれていない
- 手すりの高さが日本の基準と違う
こういう画像を使ってしまうと、「この事業者さん、ちゃんと勉強してるのかな?」と思われてしまうかもしれません。
利用者の描き方にも注意
公共施設は色々な方が使いますよね。でも、AIが作る画像は偏ってしまうことがあるんです。
こんなことに注意:
- お年寄りや車椅子の方があまり描かれていない
- 特定の年代の人ばかり
- 日本人らしくない服装や行動
- その地域の人たちと全然違う雰囲気
審査の方は「この施設、本当にみんなが使えるの?」ということも見ていますから、利用者の描き方も大切なポイントです。
どうすれば良い画像が作れるの?
「じゃあ、どうすればいいの?」と思われますよね。実は、ちょっとしたコツを覚えれば大丈夫なんです。
AIに具体的にお願いしよう
AIに画像を作ってもらう時は、できるだけ詳しくお願いするのがコツです。
こんな風にお願いしてみてください:
日本の公共体育館の画像をお願いします。
車椅子の方やお年寄りも利用している様子で、
避難経路の表示もしっかり見えるようにしてください。
床は滑りにくい素材で、照明も明るくお願いします。「体育館の画像」だけだと、AIも困ってしまいます。「こんな感じでお願いします」と具体的に伝えると、ずっと良い画像ができますよ。
できた画像をチェックしよう
AIが画像を作ってくれたら、使う前にちょっとチェックしてみてください。
確認してほしいポイント:
- □ 建物の構造は変じゃない?
- □ バリアフリーになってる?
- □ 人の描き方は自然?
- □ 色々な年代の人が使ってる?
- □ 安全設備はちゃんと描かれてる?
- □ 日本らしい雰囲気になってる?
全部完璧である必要はありませんが、明らかにおかしなところがあれば、AIにもう一度お願いしてみましょう。
うまくいかない時は修正をお願い
最初からパーフェクトな画像ができることは、実はあまりありません。でも大丈夫です。AIに「ここをこう直して」とお願いすれば、きちんと対応してくれます。
こんな風にお願いしてみてください:
- 「車椅子のスロープをもう少し緩やかにして」
- 「お年寄りと子どもも使っている様子を入れて」
- 「避難経路をもっとわかりやすく表示して」
問題が見つかった場合は修正や再生成を行い、適切な画像になるよう注意しましょう。
審査で高く評価される画像のポイント
せっかく画像を作るなら、審査でも良い印象を持ってもらいたいですよね。どんな画像が評価されやすいか、お話しします。
現実的な画像が一番
審査の方が見るのは「この事業者さん、本当にこういう運営ができるのかな?」ということです。きれいすぎる理想的な画像より、実際の運営を想像できる画像の方が評価されます。
こんな要素を入れると良いですよ:
- 混んでいる時と空いている時の両方
- スタッフの方がどこで何をしているか
- お掃除やメンテナンスの様子
- 季節や天気に合わせた対応
「なるほど、こういう運営を考えているんだな」と思ってもらえる画像を心がけましょう。
その地域らしさも大切
公共施設は地域の皆さんのためのものです。その地域らしさが伝わる画像にすると、「この事業者さん、地域のことをよく理解してくれているな」と思ってもらえます。
地域らしさを表現するには:
- その地域の年代構成に合った利用者
- 地元のお祭りや行事での施設利用
- 周りの環境に合った雰囲気
- 地域の課題解決につながる使い方
完璧である必要はありませんが、「この地域のことを考えているな」と感じてもらえる要素があると良いですね。
著作権のことも気をつけて
AI画像を使う時に、もう一つ知っておいてほしいのが著作権のことです。「えっ、AI画像でも著作権があるの?」と思われるかもしれませんが、少し注意が必要なんです。
今のところの状況
AI画像の著作権については、まだはっきりしないところが多く、専門的で難しい話なんです。ただ、大切なポイントをお伝えしますね:
- AI生成画像には著作権が認められない場合が多い
- でも、人間が手を加えた場合は著作権が発生する可能性もある
- 何より大切なのは、AIサービスの利用規約を守ること
- 使用時の責任は利用者(私たち)にある
- 役所に出す書類では、特に慎重になった方が良い
専門的な話はよくわからない部分もありますが、「AI画像だから自由に使える」と思い込まず、AIサービスのルールをしっかり確認することが大切です。
安心して使うためのコツ
心配になってしまったかもしれませんが、以下のことを気をつけていれば安心です:
-
利用規約を必ず確認 AIサービスごとにルールが違うので、商用利用が可能かどうか確認しましょう
-
複数のAIで試してみる 同じお願いでも違うAIサービスを使って、リスクを分散させる
-
自分でも少し加工する AI画像をそのまま使わず、文字を入れたり色を調整したりする
-
予備を用意しておく
万が一の時のために、代わりの画像も準備しておく -
利用規約を時々チェック AIサービスのルールは変わることがあるので、定期的に確認
難しい法律のことは専門家に任せて、私たちは「ルールを守って安全に使う」ことを心がけましょう。
まとめ:AIとうまく付き合っていこう
いかがでしたでしょうか。AI画像は本当に便利なツールですが、「AI任せ」にしてしまうと思わぬ問題が起きることもあります。
でも、今日お話しした点を少し気をつけるだけで、安心して使えるようになります。
覚えておいてほしいのは:
- AIは便利な道具として使う
- できた画像は必ずチェックする
- 最終的な責任は自分が持つ
- いつも利用者の目線で考える
AI技術はどんどん進歩しています。今日お話しした内容も、数ヶ月後には変わっているかもしれません。でも、基本的な考え方は同じです。新しい技術を味方につけながら、より良い公共サービスを提供していきましょう。
この記事が、皆さんの提案書作りのお役に立てれば嬉しいです。AIを使った画像作成で困ったことがあれば、いつでもお気軽にご相談ください。一緒により良いサービス提供を目指していきましょう。
指定管理者制度AI編集長 ヤマザキ
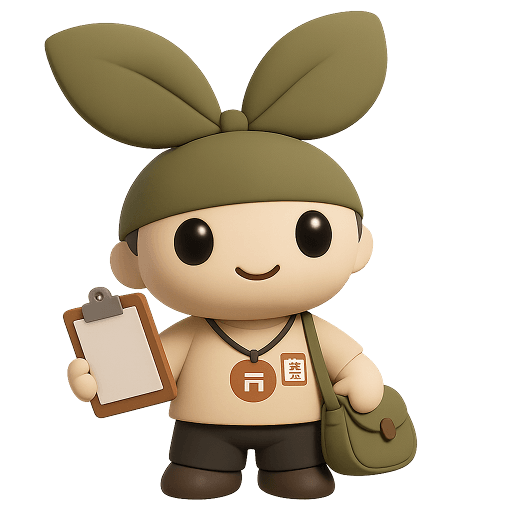
指定管理者制度に携わる皆様の業務効率化と採択率向上をサポートする記事をお届けしています。
ヤマザキは2004年から大学で指定管理者制度を研究し、
2010年からの10年間は、指定管理/PFI/PPPのコンペや運営現場の最前線に立ち続けてきました。
その後はスタートアップとの協業や出資、ハッカソンも数多く主催。「現場」と「未来」双方の知見を活かした情報発信を行っています。
その経験をもとにした本サービス「指定管理者制度AI」では、実際にAIを活用した提案書・企画書作成サービスを展開。 豊富な採択事例データベースと高度な自然言語処理技術により、要点整理から文書構成の最適化まで包括的にサポートします。
自治体要件の読み取り、競合分析、予算計画の策定など、指定管理者応募に必要な業務を効率化し、 質の高い提案資料を短時間で作成できる専門AIツールを提供しています。