
指定管理者のための「AIが勝手に考えてくれる」魔法の会話術
「AIに質問しても、いまいちな答えしか返ってこない...」そんな悩みを解決する魔法の会話術をご紹介。AIに「逆質問してもらう」だけで企画の質が劇的アップ!60点の提案を100点に変える方法、ありきたりなアイデアから脱出する2ステップなど、指定管理者の実務に直結する実践テクニックを分かりやすく解説します。
公開日2025/07/31
目次
「また同じような企画書を作らなきゃ...」「今度のイベント、何をやったらいいんだろう...」「利用者アンケートを見ても、結局何をすればいいかわからない...」
指定管理者として働いていると、こんな悩みが毎日のように頭をよぎりませんか?実は、AIとの話し方をちょっと変えるだけで、こうした問題がびっくりするほど簡単に解決できる方法があるんです。
この記事を読むとこんなことがわかります
• AIに「逆に質問してもらう」だけで、企画の質が劇的に上がる方法 • 「ありきたりな提案」から脱出して、他とは違うアイデアを生む2ステップ • 提案書や報告書を「60点→100点」に確実にレベルアップさせるコツ • 利用者の年齢や性格に合わせて、文章の「温度感」を自由に調整する技 • 「普通じゃ思いつかない」斬新なアイデアをAIに出してもらう裏ワザ
なぜ普通にAIに聞いても、いまいちな答えしか返ってこないのか
答え:AIは「あなたの事情」を全然知らないから
考えてみてください。AIは、あなたの施設がどんな場所で、利用者がどんな人たちで、予算がいくらで、自治体からどんな要望があるのか、何も知りません。
でも私たちは普段、「高齢者向けイベントを考えて」みたいに、ざっくりとした質問をしがちです。これじゃあ、AIも一般的な答えしか返せないんです。
例:高齢者向けイベントを考える場合
いつものやり方: 「高齢者向けの健康イベントを企画して」 → 「ラジオ体操やウォーキング教室はいかがでしょう」(どこでも聞く話...)
新しいやり方: 「高齢者向けの健康イベントを企画してください。いい提案をするために、私に質問があったら遠慮なく聞いてください」
すると、AIはこんな風に聞き返してきます:
- どんな施設ですか?(公民館?体育館?)
- 参加者の年齢層はどのくらい?
- 予算はどのくらいで考えていますか?
- 施設にはどんな設備がありますか?
- これまで人気だったイベントはありますか?
- 自治体から何か特別な要望はありますか?
こうやって詳しく聞いてもらってから答えると、あなたの施設にピッタリの企画が出てくるんです。
AIに「考えてもらう」ための3つの魔法の方法
1. 「逆質問してもらう」作戦
やり方: 普通の質問に、この一文を付け足すだけ 「いい提案をするために、私に質問があったら遠慮なく聞いてください」
使ってみよう:
「利用者満足度を上げる方法を考えてください。
いい提案をするために、私に質問があったら遠慮なく聞いてください。」すると、AIが「現在の満足度はどのくらいですか?」「どんな不満が多いですか?」「予算はどのくらい使えますか?」って具体的に聞いてくれます。
これに答えていくと、あなたの施設の状況をしっかり理解した、実際に使えるアイデアが出てきます。
2. 「普通の答え→特別な答え」の2段階作戦
やり方: まず普通の答えを聞いて、それから「普通じゃないアイデア」を頼む
例:コミュニティセンターの利用者を増やしたい場合
1回目:「コミュニティセンターの利用者を増やす方法を教えてください」
(普通の答えが返ってくる)
2回目:「今の答えは一般的すぎます。他ではやっていない、うちならではの面白いアイデアを考えてください」この方法で、他の施設がやっていない、あなたの施設だけの特別な企画が生まれます。
「60点の提案」を「100点の提案」に変える魔法
「点数をつけて改善してもらう」方法
これはすごく効果的な方法です。
手順:
- まず普通に提案を作ってもらう
- 「この提案を60点とします。100点にするには何が足りませんか?」と聞く
- 「じゃあ、それを追加して100点版を作ってください」と頼む
実際にやってみよう:
「上記の事業計画書を60点とします。
自治体に『素晴らしい!』と言ってもらえる100点の計画書にするには、
あと40点分、何が足りませんか?」AIが「具体的な数値目標が不足」「地域の特色が薄い」「利用者の声が少ない」などと教えてくれるので、それを改善した完璧版を作ってもらえます。
「文章の温度感」を数字でコントロールする方法
利用者に合わせて、文章の雰囲気を調整できる便利な技です。
例:施設の案内文を作る場合
「施設利用の案内文を作ります。
堅い感じ0点:『よろしく〜』みたいなノリ
堅い感じ100点:『ご利用いただきありがとうございます』みたいな正式な感じ
堅い感じ70点くらいの案内文を作ってください」この方法で、子ども向けには親しみやすく、高齢者向けには丁寧に、というふうに使い分けができます。
「普通の限界を超える」アイデア出し
一番面白いのがこの方法。普通の基準を「わざと超えさせる」んです。
例:
「地域との結びつき150点、200点の施設運営アイデアを考えてください
(100点を大きく超える、今までにない地域密着のやり方で)」すると、「普通なら思いつかない」レベルの斬新なアイデアが出てきます。
実際の現場でこう使う
場面1:利用者アンケートの活用
よくある悩み: アンケートは取ったけど、結局何をすればいいかわからない
新しいやり方:
「利用者アンケートの結果を見て、具体的な改善案を考えてください。
的確な提案をするために、私に質問があったら遠慮なく聞いてください。」AIが「アンケートの具体的な内容は?」「予算の制約は?」「スタッフの人数は?」と聞いてくれるので、実際にできる改善案が出てきます。
場面2:年次報告書作り
よくある悩み: 数字を並べただけの報告書になってしまう
「60点→100点」作戦を使う:
「上記の年次報告書を60点とします。
自治体の人が『この指定管理者はすごい!』と思う100点の報告書にするには、
何が足りませんか?」場面3:新しいイベント企画
よくある悩み: いつも似たような企画になってしまう
「普通→特別」の2段階作戦:
1段階目:「○○施設でのイベント企画の基本を教えてください」
2段階目:「それを踏まえて、独創性150点の前例のない企画を考えてください」実際にやってみた人の話
ある公民館の館長さんの体験談です:
「最初は『本当に効果あるの?』と思っていました。でも、講座企画でAIに質問してもらう方法を試してみたら、『参加者の年代は?』『過去の人気講座は?』『地域の特徴は?』と次々に聞かれて。
答えているうちに、自分でも気づいていなかった地域のニーズが見えてきたんです。最終的に『3世代で楽しむデジタル体験教室』という企画ができて、これが大当たり!定員の3倍の応募があって、満足度も98%でした。
60点→100点の方法で企画書も完璧になり、自治体からも『今までで一番いい提案』と褒められました。もう元のやり方には戻れません。」
今日から始める簡単3ステップ
難しく考える必要はありません。今抱えている悩みに、この一文を付け足すだけで始められます:
「いい提案をするために、私に質問があったら遠慮なく聞いてください」
最初は少し面倒に感じるかもしれませんが、AIとやりとりしているうちに、自分でも気づかなかった問題や解決策が見えてきます。利用者に喜ばれて、自治体に信頼される施設運営への第一歩を、今日から始めてみませんか?
まとめ:AIとの会話が変われば、仕事が変わる
この方法で何が変わるか
- AIに逆質問してもらうことで、あなたの施設にピッタリの提案が出てくる
- 普通→特別の2段階で、他とは違うアイデアが生まれる
- 点数をつけることで、提案の質が目に見えて上がる
期待できる効果
- 提案書や報告書のレベルアップで、自治体からの信頼度アップ
- 他にはない面白い企画で、利用者の満足度大幅改善
- 仕事が効率的になって、利用者対応により時間をかけられる
指定管理者の皆さん、AIは単なる便利ツールじゃありません。あなたの経験と一緒になって、もっといい施設運営を実現してくれるパートナーです。一方的に指示するんじゃなくて、お互いに話し合いながら答えを見つける。その変化が、あなたの施設に新しい可能性をもたらします。
数字で管理して、会話で創造する。これが新しい指定管理者のスタイルです。
編集長ヤマザキ(指定管理者制度AI)
参考書籍
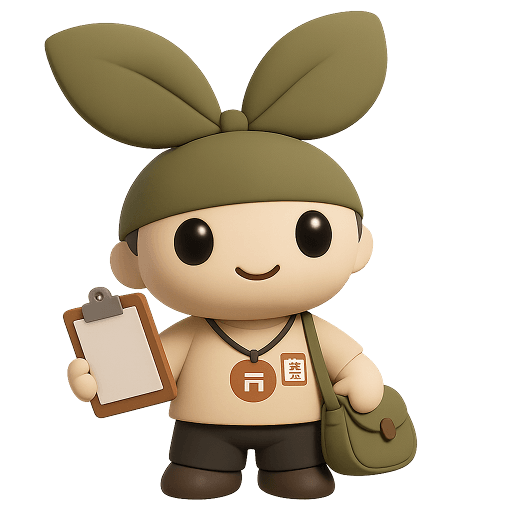
指定管理者制度に携わる皆様の業務効率化と採択率向上をサポートする記事をお届けしています。
ヤマザキは2004年から大学で指定管理者制度を研究し、
2010年からの10年間は、指定管理/PFI/PPPのコンペや運営現場の最前線に立ち続けてきました。
その後はスタートアップとの協業や出資、ハッカソンも数多く主催。「現場」と「未来」双方の知見を活かした情報発信を行っています。
その経験をもとにした本サービス「指定管理者制度AI」では、実際にAIを活用した提案書・企画書作成サービスを展開。 豊富な採択事例データベースと高度な自然言語処理技術により、要点整理から文書構成の最適化まで包括的にサポートします。
自治体要件の読み取り、競合分析、予算計画の策定など、指定管理者応募に必要な業務を効率化し、 質の高い提案資料を短時間で作成できる専門AIツールを提供しています。